ヒマラヤンの毛並みはうっとりするほど美しい一方で、飼い主の日々の努力が欠かせません。
わが家の6匹も、気が抜けるとたちまち毛玉だらけになってしまうことは頻繁に起こります。
ヒマラヤンを飼うことは毛玉との戦いです。
この記事では、私が飼い主として毛玉とリアルに格闘する日々の体験や、役に立った工夫、
逆に「これは失敗だった」と思ったシーンまで、等身大のエピソードを交えてお伝えしますね。
なぜ長毛種の猫には毛玉ができやすいのか?

ヒマラヤンの毛はとても細くて柔らかいので、普通に触れあっているだけでもすぐ絡まってしまいます。
わきの下やお腹、後ろ足の付け根などが特に毛玉スポット。
わが家では梅雨や換毛期など、湿度や抜け毛が増える季節になると一気に毛玉が増えます。
本当に油断できないのは、数日間さぼっただけであちこちに硬い塊ができてしまうこと。これは今でも毎日実感する悩みの種です。
進行するとフェルト状になりカチコチに固まった毛玉が出来上がっていきます。

猫たちにとっては皮膚が引っ張られ痛みの原因になるので、毛玉ができたら早めの対処が必要です。
毛玉発見!まずはブラッシングで対処!
三十数年前、最初にウチの子になったキャメルの脇に固い塊を発見。毛をかき分けると根元まで絡まった毛玉が…。
毛玉を見つけた時、最初にやるのはとにかく手でやさしくほぐしてみること。
硬い場合はブラシやコームを使いますが、固まっている毛玉は無理にとかそうとすると猫がすごく嫌がります。
私も昔、痛がる猫を見て「無理に引っ張るのは絶対ダメだ」と学びました。
この段階で深追いしない勇気が大切だと、何度も実感しています。
次の一手、ハサミで対処【初心者は注意!】
手やコームでダメならば次の一手、ハサミで毛玉を切る行為へと続きます。
長毛種猫初心者には絶対におすすめできませんが、きっと誰もがハサミを使おうと頭に思い浮かぶと思います。
まずはハサミを使った私の失敗談をお伝えします。
三十数年前、長毛種初心者の私は猫の皮膚が伸びることを知りませんでした。
初心者の頃、必死で毛玉を切ろうとして猫の皮膚まで切ってしまった苦い経験があります。
毛玉をしっかり持ったつもりが、皮膚の薄さや柔らかさを見誤ってしまい、猫も大きく鳴き、本当に申し訳なく思いました。
それ以降、ハサミを使うときは必ず刃先を上に向けて“少しずつ・慎重に”を徹底。
無理を感じたら一度手を止めて猫の様子を見て「できない時は絶対に一人でやらない」と決めています。
とても可愛そうなことをしてしまいました。
幸い血が流れるような大きな怪我ではなかったものの、自分が皮膚を切られたらどんなに痛いかと考えるとキャメルには申し訳ない気持ちになり大反省。
毛玉は広範囲の皮膚を引っ張てきています。そのため毛玉の元を切ろうとすると皮膚も一緒に切ってしまう可能性があるのです。
この経験から、「安全な道具と手順が大切」だと痛感しました。
今でもハサミを使います。まずは毛玉がで出来ている皮膚の状態を確認し、刃先が上を向いているトリミング用のハサミを使います。
猫の毛玉をハサミで切るときには以下のことに注意してください。
- 皮膚と毛玉ができている場所にハサミが入る余地があるのかを確認
- 刃先は下を向けない。刃先を下に向けると皮膚を切ります。「刃先は上、刃先は上」と呪文の言う。
- 大きな毛玉でも少しづつ・根気よく切っていく。
- 絶対に無理をしない。
しかし、大きな毛玉をハサミで切っていく作業は効率が悪く猫にケガをさせる危険性が大きい行為です。
ハサミを使用する際は最大の注意を払い皮膚を切らないようにご使用ください。
特に長毛種初心者の方や不器用を自負する方は、なるべく使わない方が双方のためです。
自宅でバリカン処理に挑戦
できてしまった毛玉の最終手段が次のどちらかとなります。
🐈動物病院やトリミングサロンでカットしてもらう
- 長所:トリミングのプロに任せることで綺麗にカットしてくれる。仕上がりも美しい。
- 短所:費用が高い。地域差はありますが1匹あたり数千円かかる。また猫のトリミングサロンは病院に併設している場合が多く、麻酔を掛けられて施術されることもある。
🐈自宅にてセルフケ
- 長所:自宅でできる。費用が掛からない。
- 短所:素人がカットするため見た目が悪い。家の中が毛だらけになる。猫に嫌われる。
私が選んだのはセルフケアです。猫のトリミングサロンが少ないのもあり、また動物病院に預けることは猫たちのストレスにもなります。
自宅ケアのためにペット専用の静かなバリカンを選びました。猫たちがビックリしないよう、
最初は短時間だけスイッチの音に慣れさせるところから。おやつで気をそらせつつ、できるだけ猫の負担を減らす工夫も忘れません。
慣れない頃は家族に保定を頼んで安全第一で。
焦って一気にやろうとしたとき、皮膚にバリカンを当てすぎてしまい、赤くなってしまったことがあったので、
“様子を見ながら回数を分けて少しずつ”が基本です。
そして、使いやすさではコードレスですが一番ですね。
静音設計のコードレスタイプがおすすめです。替刃も数種類付いており部分カットにも対応できました。
【余談】 私が一番静かで安全だと思ったのは人間用のバリカンでした。
主人の頭をバリカンで刈っていたときに、ふと猫の毛を刈ってみようかなと思い、人間用のバリカンを猫に使ってみました。
人間用ですので安全を考慮されており音も静か。使いやすい!と感動しました。
【必見!】自宅バリカンのやり方とコツ
1.猫たちの環境を整える
猫はカットされること(拘束されること)をとても嫌います。カットされると悟られないようにそれとなくトリミングの準備をしています。
まずは静かな部屋で猫がリラックスできるようにします。お気に入りのチューブタイプのおやつも準備しておくと安心です。暴れ出したら即座に食べさています。
2.トリミングの準備
バリカンの前に猫の爪を切っておくをおススメします。イヤなことをされているので多くの猫は暴れます。爪でケガをしないように対策をしてください。
エリザベスカラーがあればエリザベスカラーを準備する。
テーブルなど、ちょっと上でカットする方が楽です。テーブルにレジャーシートを広げるておくとカットした毛の片づけがとても楽です。
カットする人はビニール素材のエプロンを付けると毛だらけになりません。長毛種は柔らかい毛の猫ですのでかなりの毛が服に付着します。ビニール素材のエプロンがおススメです。
今ではある程度、一人できるようになりましたが、やっぱり二人でする方がおすすめです。
足や手の関節を握ると猫は身動きができなくなるので、関節を優しく握るといいようです。(動物病院で聞きました)
爪切りを嫌がる猫の頭にカップを被せるとおとなしくなる。という商品もありますので、利用されるのもひとつです。
家族に保定を手伝ってもらうと早くカットを終わらせることができます。猫の安全を第一に考えましょう。
3.毛玉の根元を確認
バリカンを入れる前に、毛玉の位置と皮膚との距離を確認します。刃が皮膚に触れないよう慎重に操作。
4.短時間で区切る
押さえつけられてバリカンで刈られている猫には大きなストレスがかかっています。
一気に全部を終わらせようとせず、数分ずつ・数日など何回かに分けての作業がおすすめです。

猫にとってはとてもイヤなことをされています。カットする際には猫の安全とストレスを減らすことを心がけています。
【再びの失敗談】バリカン負けに注意!

毛玉だけならカットの範囲はせまいのですが、全体を切る「ライオンカット」を初めてしたときに失敗をしてしまいました。
肌の近くを刈っていくうちに肌が赤くなってしまいました。いわゆる「バリカン負け」です。
皮膚に直接バリカンが当たりすぎたのが原因で、数日間はヒヤヒヤしました。
赤い肌を見ると可哀そうで辛かったです。
幸い、自然に治りましたが、皮膚トラブルを防ぐには最低限の範囲で済ませるのがベストですね。
毛玉予防のためには努力が必要!
今では、毛玉ができないよう予防に力を入れています。しかし残念ながら毛玉はできます。
長毛種を飼ういうことは毛玉との戦いです。以下の記事でもご紹介していますので一緒に読んでみてください。
関連記事 初心者でも簡単!ヒマラヤンのお手入れ方法【ブラッシング編】
毎日少しでもいいのでブラッシングすることが一番の毛玉予防だと身をもって感じています。
うちでは部屋ごとにブラシを置いて、見かけた時や猫がくつろいでいるときにすぐ手入れができるように工夫。
特に換毛期は、いつもより丁寧に根元から優しく梳かします。気難しい子にはおやつや声がけで気をそらしながら、無理をしないのが長続きのポイントになります。
細かい部位ほど見逃しやすいので、毎回「脇」「首下」「おしり」など決まった順でブラシするルールを決めています。

とにかく努力、努力の毎日です。長毛種を飼う責任を問われるのが毛玉です。猫たちと一緒に頑張ってくださいね。
おわりに|猫と暮らすなら「毛玉との付き合い方」を学ぼう!
毛玉ケアは美しい毛並みのためだけでなく、猫の健康や飼い主との信頼関係のためにも大切なことだと毎日感じています。
失敗や試行錯誤を重ねる中で、猫たちのちょっとした仕草やSOSサインにも気づきやすくなりました。
これからも猫たちと相談しながら、自分たちにいちばん合ったケアを見つけていきたいと思います。
失敗もまだまだたくさんあります。今では「毛玉ができる前に防ぐ」ことを意識するようになりました。
それでも残念ながら毛玉はできます。

しかし、猫にとっても私にとっても、快適な暮らしが続くようにこれからもお手入れを頑張っていきたいと思います。
※本記事は筆者の個人的な経験に基づいており、すべての猫に当てはまるわけではありません。心配な場合は獣医師やプロのトリマーに相談してください。
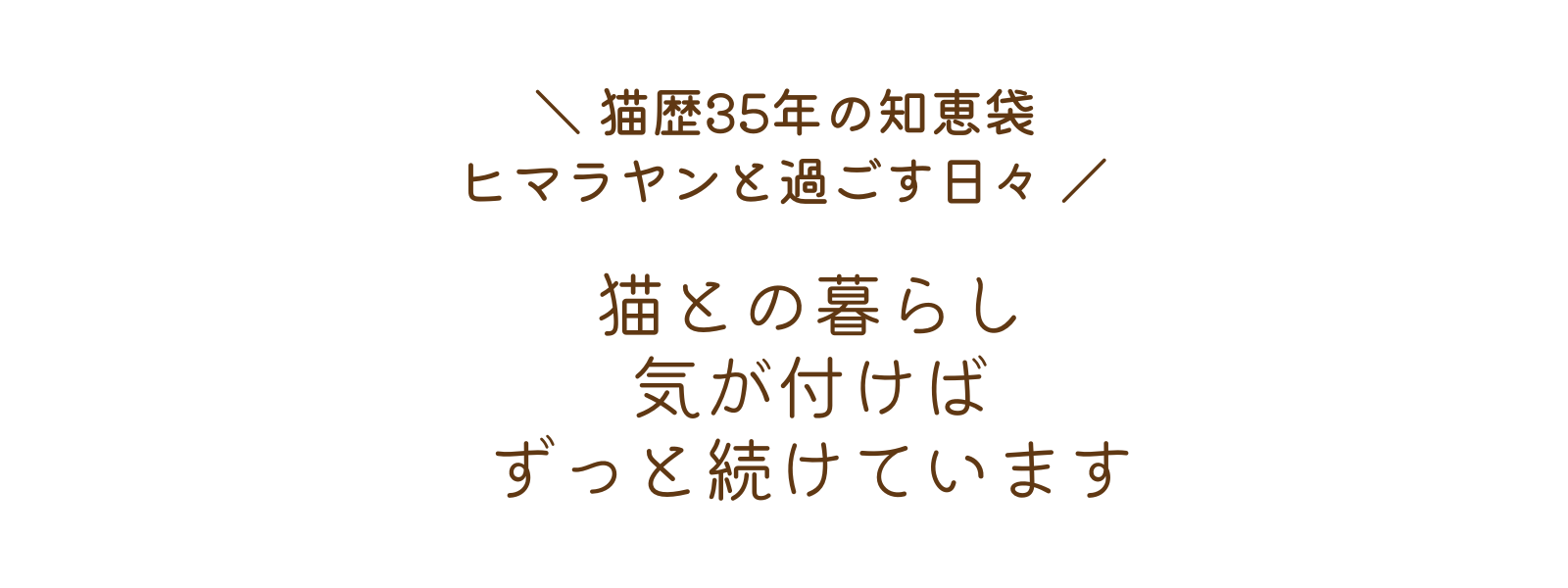



コメント