
最近の新聞やニュースは「南海トラフ巨大地震」についての報道が多く、該当地域に住んでいるいため不安を感じることが増えてきました。
私の家には6匹の猫がいます。毎日、彼らの寝顔や遊ぶ様子に癒されながらも
「もし大きな地震や台風が来たら、この子たち全員をどうやって避難させればいいのだろう?」とちゃんと考えなければいけないと思い始めました。
実は、避難訓練にすら参加したことがなかった私ですが、2024年の夏、近所で大きな竜巻が発生したときに
初めて「本当に明日は我が身かもしれない」と実感しました。
この出来事がきっかけで、猫たちと一緒に避難するための具体的な準備を始めました。
猫6匹との非難について、普段から準備しておかなければと強く感じます。
本記事では、多頭飼いの猫たちを連れて避難するための備えや、家庭でできる情報収集の方法について、実際の経験や調査をもとにお伝えします。
「猫と避難」は可能?まずは調べてみることから
まず、猫を連れて避難すること自体は可能です。
ただし、避難所の受け入れ体制や、他の避難者との兼ね合い、猫自身のストレスなど、考えなければいけない課題がたくさんです。
我が家は多頭飼いということもあり、「避難所で受け入れてもらえるのか?」「他の動物と一緒になって大丈夫なのか?」という非常事態の状況の中、
周りの方々のことも考えると簡単にはいきません。
とはいえ、猫たちは大切な家族です。置いて逃げる選択肢はありません。
だからこそ、「事前の備え」と「正確な情報収集」が、猫たちと一緒に避難するために大切なことです。
天災時の避難方法について考えていきたいと思います。
家庭でできる情報収集の方法
まず最初に私が行ったのは、住んでいる市の公式サイトをくまなくチェックすることでした。
「○○市 ペット 避難所」と検索しても、はっきりした記載が見つかららず、「ペットとの同行避難について」という項目はありませんでした。
避難所によっては「屋外に専用スペースあり」と限定することもあるようです。避難する前に具体的な内容をチェックすることが大切です。
自治体に動物と避難できるのか、電話で問い合わせてみた
市のホームページで確認ができませんでしたので電話をすることにしました。
電話で担当の方と話しができましたが「原則としてペット同行避難は可能ですが、動物と人は別のスペースになります」との説明を受けました。
動物と一緒に避難できる場所は、避難時に設定するとの回答でした。
ペットと人とは別のスペース。この言葉に不満と不安を覚えましたが、世の中には動物が苦手、またアレルギーがある方もいらっしゃいますので当然なことだと納得しました。
そして、電話を切った後、今回知り得た情報を家族で情報を共有しました。
災害が起こったときにどう動くべきなのか、どうするのか。家族で話し合うことができました。
特に我が家は6匹の大所帯。簡単には避難できないことも分かっているので、災害時にどう行動すればいいのかを家族で確認することができました。
自治体に確認する。いざとなった時にどう行動するのか家族で確認する。
自分自身で「猫たちを守る行動する」ことを考えるきっかけになり、安心につながると実感しました。
こうした具体的な情報は、災害時に慌てないためにも、事前に押さえておくべき情報ですので実践してみてください。
地域の防災訓練に参加する
地域によっては、ペット同伴を前提とした防災訓練を行っていることもあります。
私が住んでいるマンションは年に一度、避難訓練は義務として行われています。
今年(2024年)の避難訓練は、動物も一緒に避難することが訓練の一つにあがっていました。
しかし我が家が多頭飼い。猫たちは家でお留守番でしたが、今回の避難訓練を通して避難所の構造や受付方法を知ることができ、非常に参考になりました。
同じようにペットを飼っている方と情報交換できるのも大きな収穫でした。
SNSや地域アプリを活用する
災害時のリアルタイム情報は、SNSや地域密着型アプリが役立ちます。私は地域自治体(市役所)のlineを登録しています。
「#○○市 避難」「#猫 同行避難」などのハッシュタグを使って検索すると、実際に避難した方の投稿や体験談を見つけることができます。
台風時、避難勧告が出されて時に、SNSに「動物と避難される方は、ウチが受け入れます」と親切に投稿されていた保護団体がいらっしゃいました。
このメッセージは、動物を抱えて不安になっている飼い主にとってはとても安心できる投稿だったと思います。
SNSにはリアルタイムで情報があがってきますので参考になる内容が多いです。
(災害時のフェイク画像・偽サイトにはご注意くださいね)
猫との避難に向けた家庭での準備

猫ごとの避難セットを用意する
6匹の猫と一緒に暮らしていると、避難の準備も一筋縄ではいきません。
キャリーバッグは何個必要? 食料はどれくらい? 鳴き声がストレスにならないか?
――そんな心配が次々と湧いてきます。
6匹それぞれ性格も違うため、キャリーバッグも「静かな子用」「怖がりな子用」と分けて準備。
特に怖がりな猫には、普段からお気に入りの毛布をキャリーに入れて慣れさせています。
実際に避難リハーサルをしてみたところ、洗濯ネットに入れると意外と落ち着く子が多かったので、ネットも必需品リストに追加しました。
避難袋には、猫ごとにラベルを貼ったフードパックにワクチン証明書のコピー、迷子札付き首輪を入れています。
避難袋には以下のようなものを入れています。
-
フード(3日〜1週間分)
-
水と携帯用ボウル
-
猫砂(軽量タイプ)
-
小型トイレ 料理用のパットなどプラスチック製のものが軽くていいです。
-
タオルや毛布(家の匂いがついているもの)
-
ワクチン証明書のコピー
-
迷子札付き首輪
多頭飼いなので少々量がお多くなりますが、すぐに持ち出せるように人間用と一緒に準備しています。
ヒマラヤンは大型の猫ですので大きい子で5㎏が3匹います。小さい子で3㎏ですので、キャリーバックの数は多くなります。
我が家はナイロンで出来た折り畳みができるキャリーバックを用意しています。
私はベッドの下ですが、玄関の近くが便利かもしれません。
キャリーバッグやハーネスに慣れさせておく
いざ避難となったとき、猫がキャリーバッグに入るのを嫌がったり、パニックを起こす可能性もあります。
そこで、日頃からキャリーを猫の隠れ場として使っています。中におやつや毛布を入れて慣れさせています。
ハーネスについても慣れた方がいいのは分かっていますが、まだそこまで至っておりません。
ハーネルに慣れれば避難時の装着もスムーズできるのですが、まだそこまで至ってないのでこれから準備していこうと考えています。
複数の預け先を検討しておく

万が一、避難所に猫たち全員を連れて行くのが難しい場合を想定して、親族や知人、ペットホテルの候補も考えています。
最悪は自家用車の中も考えています。
多頭飼いの家庭では、一部の猫だけでも預けられるような準備が現実的です。
避難が長期化した場合にも対応できるよう、連絡先リストやアレルギー情報などもまとめてあります。
避難するタイミングと心構え
2024年の台風シーズン、実際に「避難準備情報」が発令されたとき、我が家では避難する直前までいきました。
今回、初めて避難を意識したのですが、最後の最後にキャリーバック6個を夫婦二人で持つことはとても困難であるということが分かりました。
猫の様子も普段は大人しい子が不安そうに鳴いたり、逆に怖がりの子が意外と落ち着いていたりと、想像以上に個体差があることを実感しました。
この経験から「避難は早めの判断が大切」「日頃から猫の性格に合わせた準備が必要」と痛感しました。
高齢猫や怖がりな性格の子がいる場合は、周囲の状況よりも「猫の負担が少ないタイミング」での行動が求められます。
避難は「事前の準備」と「早めの判断」が何より重要ですね。
今回、実際に避難直面まで体験して分かったことが、夫婦二人で6匹のキャリーバックを運ぶのは困難だということでした。
今、二人で対策を練っています。猫たちの命を守ることを真剣に考え始めました。
まとめ:猫も家族、だからこそ事前の備えを

「知らなかった」では、愛する猫たちを守れない。
地震や台風など、自然災害はいつやってくるかわかりません。
だからこそ、日頃から猫との避難を想定し、少しずつ準備をしておくことが大切なのです。
避難経験がないと「自分にできるのか」と不安に思うこともあります。私もそうでした。
でも、いま一緒に暮らす猫たちを守るためには「知らなかった」では済まされないのです。
多頭飼いだからこそ、日々のちょっとした工夫や家族との情報共有が、いざという時の安心につながると実感しています。
実際に自分で調べ、準備し、リハーサルを重ねてきたからこそ、「もしもの時もきっと大丈夫」と思えるようになりました。
この記事が、同じように猫と暮らす方のヒントや安心材料になれば嬉しいです。
環境省のHPにある動物愛護管理室の「ペットの災害対策」を読んでおくこともおすすめします。
「もしも」に備えることは、「今を大切に暮らすこと」につながります。大切な家族を守るために、今日からできる一歩を踏み出してみませんか?
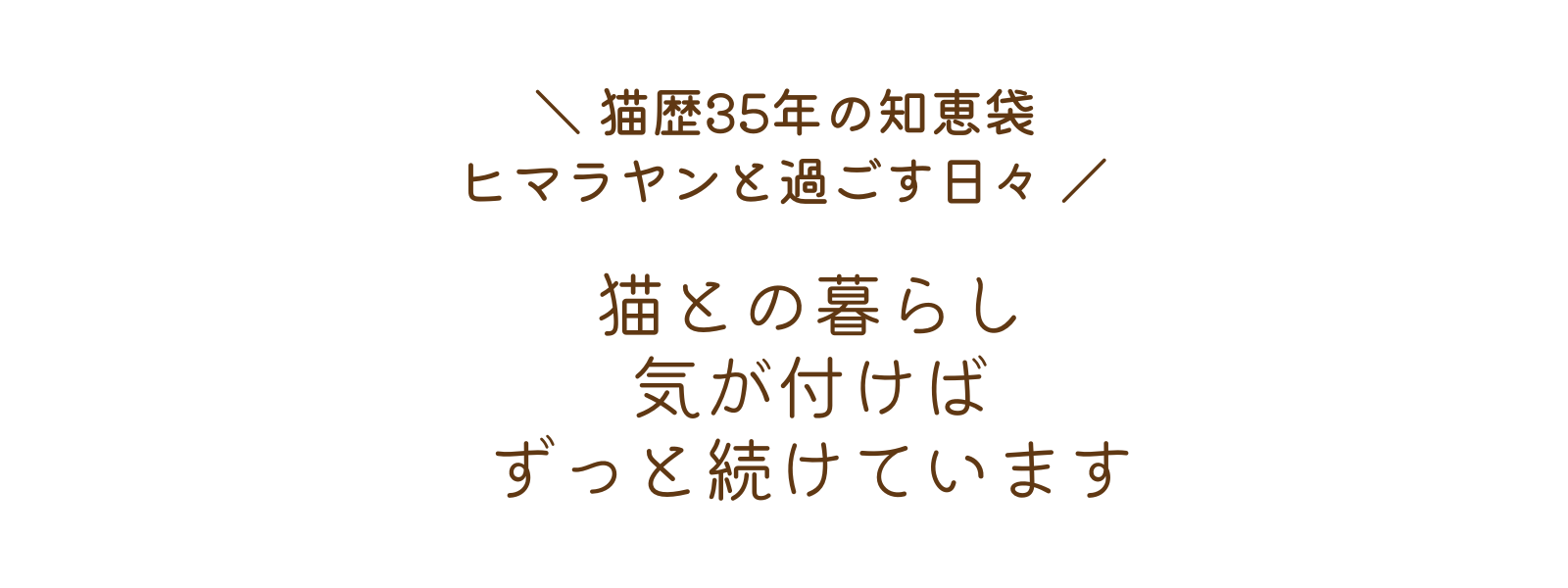
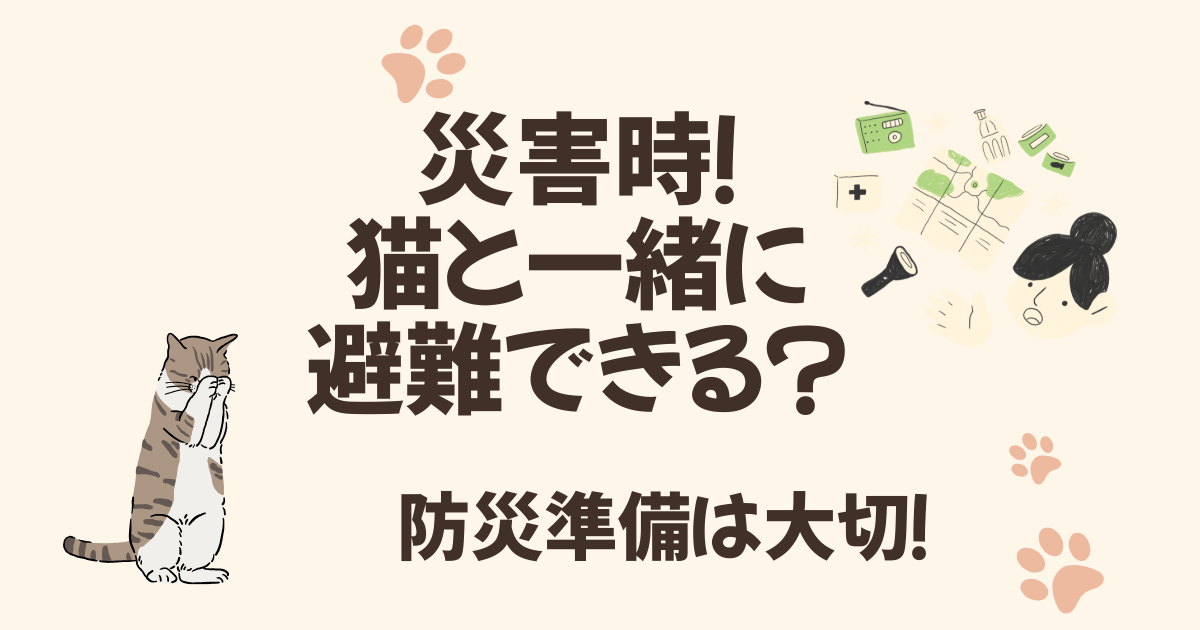

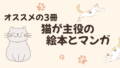
コメント