猫が自分の身体を過剰に舐めてしまい、皮膚に赤みや脱毛が生じる症状――それが「舐め壊し」です。
一見すると毛づくろいの延長のようにも見えるこの症状、実は心身の不調が隠れていることがあります。
我が家の愛猫ハナ(11歳・メス)も、この症状に悩まされたひとり。気づいた時には、すでにかなり進行していたのです。
この記事では、ハナが舐め壊しを発症したきっかけから、私たち家族が実践してきた試行錯誤の対処法
そして日々のケアで気をつけていることまで、ありのままをお話しします。
もし、あなたの愛猫にも気になる様子があるのなら、少しでもヒントになることを願っています。
最初の異変と気づき
毛並みの変化に違和感
ある日、何気なくハナのお腹を撫でていたときのことです。手のひらに触れる毛の感触が、いつもより薄く感じました。
「あれ?」と少し不安になりつつも、その場では深く考えませんでした。ちょうど換毛期だったこともあり、一時的な抜け毛だと思っていたのです。
ところが翌日、明るい部屋でよく見ると、うっすらと赤みを帯びた皮膚が見えていました。その瞬間、何かが違うと直感しました。
異常なグルーミング
それからというもの、ハナの様子が気になって仕方ありませんでした。
観察していると、同じ場所を執拗に舐め続ける姿が目につくようになりました。
特に私たちが寝静まった深夜、静かなリビングで延々とお腹や足を舐めているのです。

通常の毛づくろいは、全身をバランスよく行います。しかしハナの場合、明らかに同じ箇所ばかり。これが「舐め壊し」だったのです。
獣医師による診察と推測される原因
舐め壊しと診断
翌朝すぐに動物病院に連れて行きました。
診察を終えた獣医師は一目見て、「これは典型的な舐め壊しですね」と即答。
その言葉に驚きつつも、やはり…という納得もありました。
皮膚は軽い炎症を起こしており、放置すれば悪化するリスクがあるとのこと。
早急に対処を始める必要があると説明されました。
想定される要因
舐め壊しの原因は一つではなく、いくつもの可能性が絡み合っているそうです。獣医師が挙げた主な要因は次の通りでした。
- 食物アレルギーや環境アレルギー
- 精神的ストレス(同居猫、引っ越し、家族構成の変化など)
- ノミやダニなどの寄生虫
- アトピー性皮膚炎や真菌症
- 内分泌疾患(甲状腺機能亢進症など)
福太郎(新参猫)の存在が影響?
話を詳しく聞かれる中で、2ヶ月前に子猫の福ちゃんを迎えたことを伝えると、「それがストレスの引き金になっている可能性は高いですね」と言われました。
実際、福ちゃんが来てからというもの、ハナは静かな場所を好み、高い棚の上で過ごす時間が長くなっていました。
元気そうに見えても、心の中では戸惑っていたのかもしれません。
自宅で試した対処法の数々
エリザベスカラーとその限界
まず試したのはエリザベスカラー(通称エリカラ)です。傷口を舐めないよう首につけるもので、獣医師からも推奨されました。
ところが、装着した瞬間からハナは動かず、じっとしたまま固まってしまいました。
ご飯も食べず、水も飲まず、排泄も我慢してしまう始末。これはストレスが強すぎると判断し、装着から1日も経たずに外しました。
術後服でのカバー
次に試したのは、術後用の猫用ウェアです。
最初は違和感があるようでしたが、エリカラよりはましだったようで、徐々に慣れてくれました。
ウェアを着せている間は舐められないので、傷の回復は進みました。
ただし、脱がせるとすぐにまた舐め始める状態に戻るため、「一生この服を着続けるのか」と複雑な気持ちになったのを覚えています。
食事療法と栄養の見直し
食物アレルギーの可能性
診察の中で、食物アレルギーの可能性が示唆されたため、食事内容も見直しました。具体的には、
- 穀物不使用(グレインフリー)
- 単一タンパク源(魚のみ、鴨肉のみ等)
というフードを選びました。特に鶏肉が原因かもしれないという話もあり、思い切って魚ベースのものに切り替えたところ、皮膚の赤みが徐々に引いてきたのです。
オメガ3サプリの導入
あわせて取り入れたのが、皮膚の健康維持に良いとされるオメガ3脂肪酸。
サーモンオイルをフードに数滴垂らして与えると、食いつきも良く、毛の生え具合が改善されてきました。
ストレス対策と生活環境の工夫
安心できる居場所の確保
猫は静かな場所を好みます。そこで、普段あまり使っていなかった部屋に、キャットタワーやベッドを新たに設置。
ハナだけの“避難所”を作るようにしました。
この場所で過ごす時間が増えるにつれ、落ち着いた表情も見られるようになりました。
日課の見直し
毎日の遊び時間も見直しました。猫じゃらしで遊んだり、話しかけたり、体を撫でたり。スキンシップの時間を意識的に増やしました。
ストレスをためないようにすることは、飼い主との信頼関係にもつながる大切な時間だと実感しています。
他の猫の「舐め壊し」体験談
ノミが原因だったケース
友人の猫・ミミちゃん(5歳)は、急にお腹を舐め続けるようになり、薄毛になってしまいました。
原因は意外にもノミ。駆除薬を使ったところ、1週間ほどで症状が収まりました。
引っ越しがきっかけだったケース
知人の猫・ラグドール(2歳)は、引っ越し直後から舐め壊しを始めたそうです。
新しい環境に慣れるまでの間、安心できる場所や遊びで気を紛らわせるようにしたことで徐々に落ち着いていきました。
歯の不調が関係していたケース
猫カフェのスタッフ猫・レオン(7歳オス)は、首元を舐め続けるクセがありました。
原因がわからず検査したところ、実は歯の根に感染症があったのです。
治療後、自然と舐め行動もなくなったとのことでした。
食事が原因だったケース
私の姉の猫・チロ(3歳オス)は、新しいおやつを食べ始めた後に背中を激しく舐め続け、脱毛してしまいました。
調べたところ、着色料など添加物が原因だったことが判明。食事を変えることで改善したそうです。
実践して効果を感じた10の対策まとめ
- 原因の明確化と検査(アレルギー・寄生虫・血液検査など)
- 獣医師と連携し、必要ならセカンドオピニオンを受ける
- 食事内容の記録と反応をメモする
- 日常的なブラッシングで皮膚状態を観察
- 爪を整えて引っ掻き行動による悪化を防ぐ
- 隠れられる静かな場所の確保
- 決まった遊びの時間を持つ
- 窓辺の眺望やキャットタワーの設置
- 洗剤・芳香剤などの環境刺激を見直す
- 飼い主自身がリラックスし、猫との信頼関係を築く
まとめ:ハナとの日々から学んだこと

ハナの舐め壊しと向き合う中で、猫が発するサインに敏感になることの大切さを痛感しました。
一見すると些細な行動でも、そこには深い意味がある場合があります。
完治にはまだ至っていませんが、改善の兆しが見えるだけでも希望になります。
猫の「舐め壊し」は、単なる癖ではなく、心や身体の異常を知らせる大切な信号です。
あなたの猫が同じような症状を見せたとき、早めに行動し、向き合ってあげてください。

この記事が、同じ悩みを抱える誰かの力になれたなら、それ以上に嬉しいことはありません
。
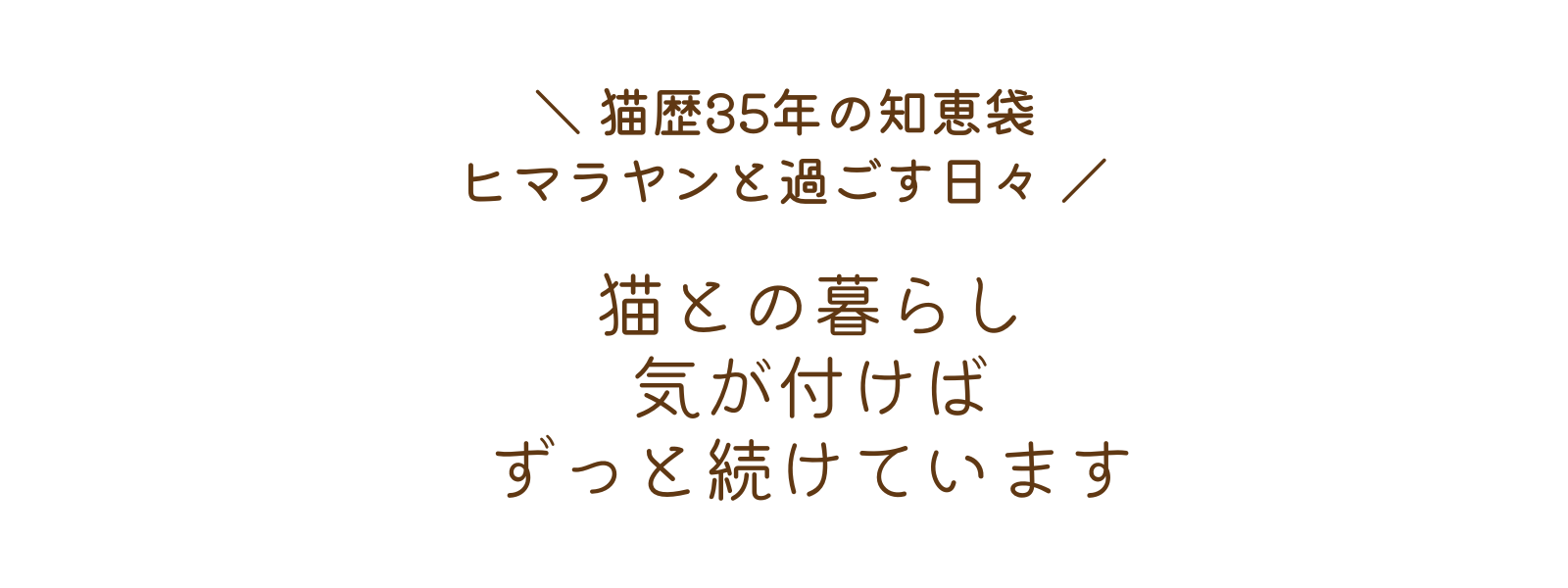



コメント